【書評】稼ぐ人の超速文章術

- 「文章をうまく書けない」
- 「文章を書くのに時間がかかる」
- 「文章が分かりづらい」
今回は「稼ぐ人の超速文章術」という本を解説いたします。
著者は中野巧さんです。共感結果につなげる「エンパシーライティング」を開発して10年間で、小学生から経営者まで、多くの人の文章改善に関わり、5万人以上に文章のノウハウを伝えています。
エンパシーライティング講座は即効性と分かりやすさが定評で、人気の講座です。
これが世界に広がることで、世界に共感があふれ、共感によってつながる、やさしい世界に貢献できると確信しています。
共感のライティング、私もぜひ受けてみたいです。
現代に必要なスキルは「文章力」
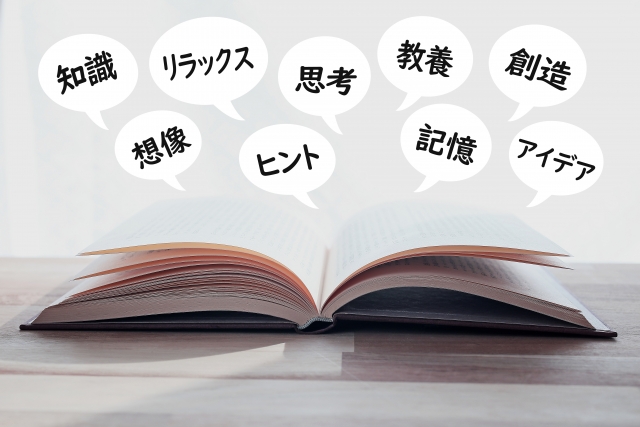
現代に必要なスキルと言えば何を浮かべますか?
- 「プログラミング」
- 「英語」
- 「コミュニケーション」
- 「マーケティング」
- 「トーク」
- 「ライティング」
などなど色々と浮かぶと思います。
その中でも、特に重要なのがライティング、つまり「文章スキル」です。
文書スキルは現代において必須となります。
なぜなら、SNSやLINE、ホームページ、ランディングページなどが当たり前になったからです。もう「文章は苦手だから」と避けてはいられない状況です。
ただ、言葉って難しいですよね。人によって捉え方も違います。
XやYouTubeでの炎上の原因は「リテラシーの低い人が誰かの発言を鵜呑みにした結果」起こります。
文書は「文字」のみで相手とコミュニケーションを取ります。顔が見えないため「正しく伝わらないこと」や「誤解が発生すること」があります。
とはいえ、文章は使いようによっては「人を動かす」最強の武器となります。
文章は「仕事」「人間関係」「メンタル」この3つに非常に良い影響を与えます。
- 「仕事」であなたのサービスが的確に伝わり、評価が上がる
- 正しく伝えることで「人間関係」が劇的に良くなる
- 文章を書くことや伝えることへの「メンタル」への負担が減る
要は文章を書くスキルは「あなたの価値を高める」最強のスキルです。
とはいっても、「文章って才能ではないの?」「努力でどうにかなるの?」という方がいるかもしれません。
文章は才能ではありません。誰もが上手くなります。
本書でお伝えしているコツを知れば、
「文章は、誰でも、確実に、上手くなる」ということです。
情報が多い現代では、何が正解なのか分かりません。
そんな中でも本書では「これだけ知っていれば大丈夫!」という知識や独自の方法論が書いています。
そして本書では「超速」を大事にしています。どんなに上手い文章が書けても、時間かかりすぎたら意味がありません。
「速く書く」これこそが時代が求めているスキルといいます。
今回の記事では「分かりやすい文章テクニック」を紹介します。
本当は著者の真髄である「共感させる文章」について書こうと思いましたが、かなり細い内容ですので、気になる方は著書を読んでみてください。
この記事では「パッと見て分かるテクニック」を書かせていただきます。
内容は次のとおりです。
- 知るだけで文章が上手くなる5つの文章のコツ
- 文章に効く5つの心理効果
- 普段からトレーニングせよ
ということで、さっそくお伝えします。
知るだけで文章が上手くなる5つの文章のコツ
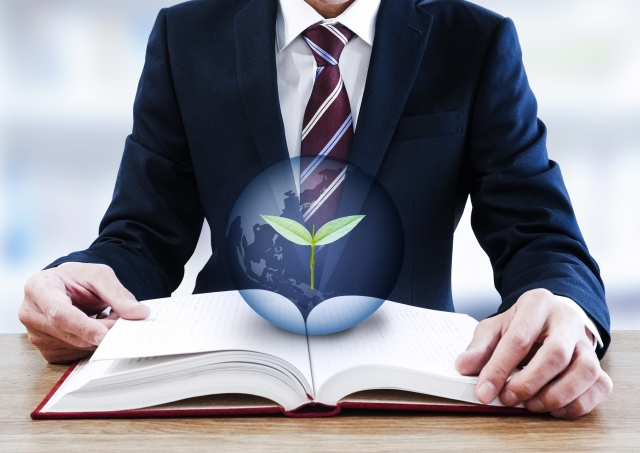
- 主語をあなたにする
- 「?」を乱用しない
- 1文50文字以内
- 相手に負担を与えない
- 説教しない
1つ1つ解説します。
主語をあなたにする
「自分視点」ではなく「読み手視点」にしよう。
たとえば、こんな文がありました。
「私は最近ブログを始めました、私はまだ初心者ですが楽しく書いています。PV数が増えると私のモチベーションが上がります」
どうでしょうか?「私」が多いと読む気なくしませんか?
このような「自分視点」の文章は読み心地は良くありません。
「私」を「あなたに」変えるなど「読み手視点」に切り替えることで、相手が読みやすい文章を作ることができます。
「?」を乱用しない
たとえば、こんな文がありました。
「先日のプレゼンはいかがだったでしょうか?どちらの方法が良いでしょうか?また打ち合わせをしたいと思いますがよろしいでしょうか?日程をいくつか教えていただけないでしょうか?」
もう恐ろしいですよね。
「?」って楽に書けるが故に、読み手に尋問されているような不快感を与えてしまいます。
乱用しすぎないように気を付けましょう。
1文50文字以内
たとえば、こんな文がありました。
「ブログを書くときは出来る限り読者さんに刺さるようなタイトルや見出しをつけたいのですがなかなか良いキャッチが浮かびづらく本やインターネットで学んでいるもののどれもパッとしません」
長文の文字って読みにくいですよね。
また、文章を書くとき「句読点や改行のない」文章は読み手疲れさせてしまいます。
基本は1文1メッセージで50文字以内がベストです。
相手に負担を与えない
分かりやすい文章を書く際に「読み手に負担を与えない」は大前提です。
相手に余計な負担を与えないように考えた想いや気遣いは、文章だけでも相手に伝わっています。
余談ですが、相手に負担を与えないという点では「メンタルモデル」を構成するのも大切です。
これは相手に先の展開をわからせるように行うものです。分かりやすい例でいうと「見出し」です。見出しを書くことで相手にこの先の展開をわかってもらえるようになります。
説教しない
言葉は使い方を間違えたら「人を傷つける武器」となります。
説教じみた「上から目線の文章」では人の心を掴むことはできません。
ただ、もちろん、何かを伝えるとき「正しさ」は大切です。
そんなときは「自分の失敗談」などをネタにすることで、相手に共感を与え、読み手にとって心地の良い文章となるでしょう。
文章に効く5つの心理効果

- プライマシー効果
- リーセンシー効果
- 見出し効果
- ツァイガルニック効果
- ハロー効果
続いては心理学を用いて、テクニックをお伝えします。
心理効果を利用すれば、文章力が上がります。本書では5つ紹介されています。
1つ1つ解説していきます。
プライマシー効果
私たちは「最初に与えられた印象」に大きな影響を受けます。
これを「プライマシー効果」です。初頭効果とも言います。
たとえば、本書のタイトル「稼ぐ人の「超速!」文章術」は興味を惹かれるタイトルだと思います。だからこそ、あなたも今、この記事をみています。
最初の印象を大事にすると、興味を持ってもらえるような文章を作ることができます。
リーセンシー効果
私たちは「直前に触れた情報(最新の情報)」から影響を受けます。
これを「リーセンシー効果」です。
たとえば、ブログの最後に行動を促す言葉があることで、読んで終わりにならない、読み手の行動につながる文章になります。
また、「スーパーのレジで並んでいるとき、なんとなく何かを買ってしまった」というのも、リーセンシー効果です。
見出し効果
見出しを読むだけで「6割くらいの内容がなんとなくわかる」が理想といいます。
たしかに見出しが具体的だとすいすいと頭の中に入ります。
忙しい現代人は文章をじっくり読む習慣がなくなっています。
そのため、見出しを具体的に、パッとみてすぐわかるような見出しが良いでしょう。
ツァイガルニック効果
私たちは完成されたものよりも未完成のものに興味が惹かれます。
これをツァイガルニック効果といいます。
たとえば、「ドラマが気になるところで次回に回される」「続きはcmの後で」などです。
ポイントポイントで次を読みたくなる謎を作ると良いでしょう。
ハロー効果
私たちは1つの特徴に引っ張られて対象を歪めて見る心理があります。
たとえば、ある有名人がおすすめするもの、があったらつい購入することありますよね。あれです。
人はものを購入するとき、「価格」「商品」「サービスの内容」「タイミング」など、あらゆる要素を考慮します。
どの要素を重視するかは人によって異なりますが、多くの方が少なからず影響を受けているのが「ハロー効果」です。
AmazonやYouTubeのおすすめ機能もこのようなハロー効果を活用しています。
普段からトレーニングせよ

普段から文章をかかないとレベルアップはしません。
ポケモンやドラクエのレベル上げと同じです。
文章のノウハウを少しでも良いので、使用してみると良いです。その小さな意識がどんどん積み上がることであなたの文章力は向上します。
そのためにも、たとえば、文章を書いたあとに
- 「表現はこれでよいか?」
- 「同じことを繰り返していないから?」
- 「文章がタイトルや見出しとずれていないか?」
このように意識することが大切です。
ぜひ、文章力を向上させたい方は、ブログやTwitterは比較的始めやすいのでおすすめです。
まだまだ足りない
今回は「稼ぐ人の超速文章術」という本を書評しました。
「分かりやすい文章テクニック」いかがでしたでしょうか?
本書で今回お伝えした内容以外にも様々なテクニックが書かれています。
- 「ブログの書き方」
- 「メルマガの書き方」
- 「SNSの書き方」
- 「ランディングページの書き方」
などなどと書かれています。
これらのようなテクニックはもちろん重要です。情報を整理し、的確に相手に届ける力は確実にこれからの時代は必要でしょう。
ただ、それだけでは「人を動かす」文章を書くことができません。
そこで本書では「共感される文章」の真髄を書いています。
「共感される文章は人を動かす」
「人を動かす」ためには「共感される文章」を書く必要があります。
共感され、より深く相手に届く文章を書けるようになれば、人を動かすことができるます。
著者は、「共感される文章」を書くためのツールとして「エンパシーチャート」を提案しています。これをすることで共感され、結果につながる文章を描けるようになります。
エンパシーチャートの具体的な説明は本書に書いています。
気になる方はぜひ、読んでみてください。





