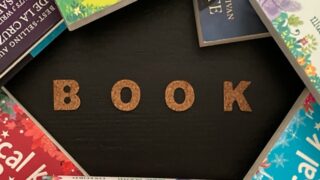【書評】読んだら忘れない読書術

「本を読んでもすぐに内容を忘れてしまう」
「人よりたくさん読んでいるのに本の内容を説明できない」
「読書をする時間がない」
今回は、精神科医の樺沢紫苑さんの「読んだら忘れない読書術」という本を解説します。
樺沢紫苑さんはインプットとアウトプットの達人です。スキマ時間に月30冊の書籍を読み、年に3冊の書籍を執筆、講演、毎日メルマガやYouTubeなどで情報発信をされています。
「どのようにしたら著者のように、アウトプットができるのでしょうか?」
その秘訣が「圧倒的なインプット」です。
圧倒的な量の情報を日々自分の頭の中に入れているからこそ「圧倒的なアウトプット」が可能となります。
その圧倒的なインプットの軸が「読んだら忘れない読書術」です。
著者が推奨するのは「自己成長を目的」とした読書であり、1冊1冊を真剣に選び、深く読む読書法です。
本書の内容は、読んだら忘れない読書術の他にも、読書で得られること、読書時間を確保する方法、本の選び方、本の買い方、電子書籍の活用方法など、読書に関することが網羅されています。
この記事では、「なぜ読書をする必要があるのか?」「読んだら忘れない読書術とは?」「読書時間を確保する方法」この3つについてお伝えしたいと思います。
なぜ読書をする必要があるのか?
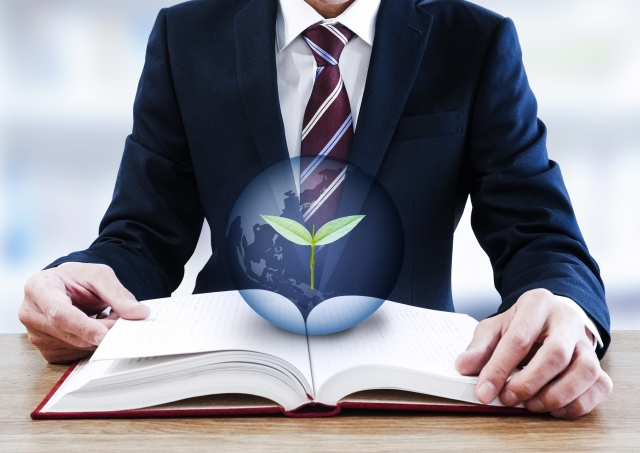
「読書なんか必要ない」
という方は一定数存在しています。
ただ、著者はこういっています。
「読書は人生に大切なものをすべて与えてくれる」と
ここでは「読書の必要性」を3つお伝えします(本書では8つあります)。
結晶化された知識が得られる
最初に「情報」と「知識」の違いをお話しします。
「情報」とは、ネットやテレビ、新聞、雑誌、週刊誌などで得られる大部分のもので、1年たったら古くなります。
「知識」とは、著者が整理をして体系的にした「本」のことで、10年たっても古くなりません。
情報は「事実」「結果」「事象」であり、知識はそれらの積み重ねから得られる「エッセンス」です。
つまり、「知識」を得られる本を読むことで、実践可能、応用可能で行動につながり、10年たっても風化しない「結晶化された知識」を得ることができます。
もちろん、ネットの中にも「知識」はあり、本の中にも「情報」だけまとめたものはありますが、ざっくりまとめるとネットは「情報」を得るもので、本は知識を得るものといえるでしょう。
要は「断片化された知識」ではなく体系的にまとめられている「結晶化された知識」の方が、一から学ぶよりも100倍楽で効率的ということです。
ただ、ネットの知識はいわゆる「トレンド」や人々の「意見」を確認できるため、「知識」と「情報」のバランスをとっていくことが大切です。
本を読めばストレスと不安から解放される
本に書かれている通りのことを実践すれば、ほとんどの場合「悩み」は解決するか軽減します。
なぜなら、人間の悩みは昔から共通しているからです。たとえば、お金の悩み、仕事の悩み、人間関係の悩み、恋愛の悩み、成長の悩みなど。
これらの「悩み」はもうすでに本に解決策が書いています。
では、どうしてほとんどの人が悩んでいるのか?
それは「本を読んでいないから」です。正確には「本を読むどころではない」という気持ちの方が強いからです。「悩み」や「ストレス」を抱えた場合は、心理的に余裕がなくなります。
本を普段から読む人は、余裕がない状態でも本を読んで解決策を見出します。なぜなら、本に解決策があると知っているからです。
ただ、本を普段から読まない人は、心理的に余裕がない状態では本を読むのは難しいです。
「解決策が分かっても、解決しないときはストレスが溜まりそう」と思う方もいるでしょう。実はこの考えは間違っています。
本書で紹介されている実験によると、「対処法、解決法を調べて「何とかなる」と分かっただけで状況が改善しなくても、ストレスの大部分がなくなる」ということがわかりました。
つまり、本は悩みを解決する軽減できると「知っている人」は、ストレスと不安に「クヨクヨ」することから解放されるということです。
読書をすると頭が良くなる
読書は「物知り」にしてくれるだけではありません。
多くの脳科学研究では、読書によって「知能が高くなる」「字頭が良くなる」「脳が活性化し、脳のパフォーマンスが高まる」ということがわかっています。
著者は本来、頭が良いとはいえない人間でした。ただ、月に30冊の読書と毎日の文章を書くことを30年以上も続けてきたことで、圧倒的に頭がよくなったと言っています。
また、人間の能力は脳を鍛えることで一生伸ばし続けることができる、と言われています。人間の能力を伸ばすためには「読書」と「運動」です。
運動に関しては、「脳を鍛えるには運動しかない」という本で解説されています。気になる方は読んでみてください。
読んだら忘れない読書術とは?

「何度も利用される情報」と「心が動いた出来事」は記憶に残ります。
脳科学的には、「最初のインプットから7~10日以内に3~4回アウトプットする」というのが最も効果的な記憶術である。
ここだけお伝えできれば良いかなと思うので、これぐらいにします。
ただ、一応著者が進める読書術を紹介します。
- 本を読みながら、メモをとる、マーカーでラインを引く。(インプット)
- 本の内容を人に話す。本を人に勧める。(アウトプット)
- 本の感想や気づき、名言をFacebookやTwitterでシェアする。(アウトプット)
- Facebookやメルマガに書評、レビューを書く。(アウトプット)
難しいと思いますが、意外と何回か練習すれば、できるようになります。
まずは愚直にやると良いでしょう。
読書時間を確保する方法
「読書をする時間は確保できます」
たとえば、サラリーマンは通勤時間、移動時間などを合計すると「1日1〜2時間」は取れると思います。
これを読書に使えば、月4冊ぐらいは読むことが可能である。
ただ、そうかんたんにできたら苦労しません。
著者はさまざまなテクニックを紹介していますが、ここでは2つだけお伝えします。
1つ目は「15分集中読み」です。
15分という時間は、脳科学的に見ても「極めて集中した仕事ができる時間のブロック」とも言われています。
スキマ時間に15分、このぐらいでしたら、続けられそうですね。
2つ目は「制限時間を設ける」です。
たとえば、「今日1日でこの本を読む!」と目標を設定します。制限時間を決めると、緊迫感が出るので集中力が高まり、ドーパミンやノルアドレナリンなど記憶に関係する脳内物質が分泌され、読んだ内容が記憶に残りやすくなる。
読書は楽しいもの
以上、樺沢紫苑さんの「読んだら忘れない読書術」という本を紹介しました。
本書では、他にも本の選び方、本の買い方、電子書籍の活用方法など、読書に関することが網羅されています。
最後に6ヶ月で300冊以上読んだ私が「読書は楽しいもの」ということで2つお伝えします。
自己成長のための読書は辛い
1つ目は「自己成長のための読書は辛い」というものです。
樺沢さんも同じことをいっています。
読書の動機は「楽しいから」であって、「自己成長のため」であってはならないと。
私は最初、「本を読んで成功するぜ」といって頑張ってたくさん読んでいました。
それが、逆にストレスになっていました。本をたくさん読んで、成功するなら、みんな読んで、いまごろみんな成功しています。
樺沢さんも、ストレスになると記憶を強化する脳内物質ドーパミンは分泌されない。楽しみながら読むと、ドーパミンが分泌されて、記憶にも残り、自己成長につながる、といっています。
つまり、楽しく読んだら結果的に自己成長につながるということです。
まずは、自分の楽しいと思える分野を探す、楽しく読んでいたら必ず自己成長につながります。
興味のある分野がないという方へ
2つ目は「興味のある分野がないという方へ」というものです。
私も最初は興味のある分野がなかったです。大学は法律を学んで、仕事は医療業界にいます。
ぶっちゃけ2つともあまり興味がありません。
どうして入った!と思うかもしれませんが、そこはご了承ください。
私はいま、どのような分野に興味をもっているかというと「心理学」や「健康系」に興味があります。
とはいえ、健康系は特別、専門的なスキルはないので、ここでは割愛します。
「心理学」というと、人が何をしたらどのような心理になるのか、人が何をしたらそのような行動をするのかなどを知るのが楽しいと思えました。
いまは心理学を飛び越えて、歴史やお金といったところまで学んでいます。
ここでいいたいのは、なにか1つの分野を楽しめたら、他の分野にも興味が出てくるということです。
ITがあらゆる産業の壁を超えてぶっ壊す、と同じで、私もいろいろなジャンルを渡り歩いています。
歩くたびに、興味が広がり、自己成長にもつながります。
最初、ほんとうにどんな分野でも良いです。
必ず楽しいと思える分野が出てきます。
まずは、よくわからないけどそれを学ぶとよいです。
そしたらいろいろなことがわかるようになり、興味もひろがり、結果的に自己成長につながり、幸せな人生を送ることができます。
ということで、今回は以上となります。
本書は読書という壁を超えて、人生にまで深く影響した本でした。ぜひ、気になる方は読んでみてください!