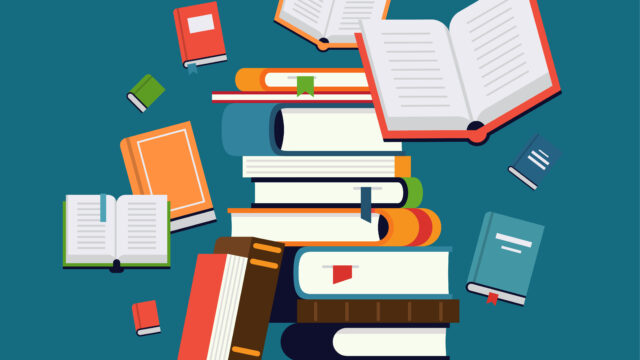【解決!文章の書き方まとめ記事】

本記事は、文章の書き方をまとめた記事になります。
構成は以下の通りです。
はじめに、『文章を書くのが苦手な人にやってほしい3つのこと』をお伝えします。ここでは、「文章を書くのが難しい」と感じている方におすすめです。
さらに、『【文章の書き方!】これだけ覚えれば文章はうまく書ける』をお伝えします。ここでは、とりあえず覚えたいという方におすすめです。
最後に、『毎日3000文字を生み出す3つのコツ』をお伝えします。あとは続けるのみです。文章を生み出すコツを知りたい方におすすめです。
非常に文章量が多いため、必ず下記目次から、『自分が知りたい』と思ったところだけを確認ください。
文章を書くのが苦手な人にやってほしい3つのこと
「文章を書くのが苦手」
「言葉が出てこない」
「どうしたら苦手を克服できるのかな」
こんな疑問に答えます。
ここでは「文章を書くのが苦手な人にやってほしい3つこと」ということでお伝えします。
「文章を書くのは難しい」
ほんとうに文章を書くのって難しいですよね。
「適当な言葉が思い浮かばない」「この言い回しであっているのかな」「どんな文章だとわかりやすく伝わるのかな」こんなことはしょっちゅう思います。
書店に行くと、「文章を上手くなる方法」というたくさんあります。それらをみても「結局うまく書けない」なんてことを経験した方もいるでしょう。
今回お伝えする内容も「書店にある文章の本」に載っているような内容です。
そしたら「この記事を読んでも意味ない」と思われるかもしれません。
ただ、文章を上手くなる方法は、もう世に溢れています。もう、どのように書けばいいのか知ることができます。
ということは「とにかく書けば」良いのです。
もしかしたら「何か秘訣」があるのでは思って、この記事を開いた方もいるかもしれません。申し訳ありません。
私は文章を上手くなる方法「とにかく書く」しかないと思っています。
今回お伝えする3つのことと「とにかく書く」を行えば、確実に文章が苦手ではなくなり、文章が上手い人になれるでしょう。
では、さっそくお伝えします。
文章を書く秘訣

最初に「文章を書く秘訣」をお伝えします。
「え!秘訣ってないんじゃないの?」
実はあります。
それは、「何を書くかというアイデアは考えているときにではなく、書いているときに生まれるものであるから」です。
野球にしてもサッカーにしても、実際に行わないと上達はしません。
文章も同じで「考えているとき」ではなく「書いているとき」に言葉が出てくるものです。
私もいま、こうして書いていますが、書いている最中はどんどんアイデアが生まれて手が進みます。
逆に「何を書こうかな」と考えているときはアイデアが生まれません。
ここまで聞いて「書けないと悩んでいるときは考えた方が良いと思う」「閃いて出てくるのも大切じゃないの?」と思う方もいるでしょう。
実際に、机に座って1時間何も書かなかったこともあります。何か考えているときに、ふとアイデアや悩みが解決する方法が浮かび上がることはあります。
作家さんは、悩んでも文章が書けなかったけど「寝て起きたら書けた」なんて話も聞きます。
ただ、たしかなことは「書かないと文章は生まれない」です。
これがどんなことにも言えます。たとえば、勉強しようといやいや参考書を開いたら「意外とできた」、バッティングセンターで絶対当たらないと思ってバットを振ったら「打てた」なんてこともあります。
このように、「何かしないと」何事も進みません。
文章が苦手という方は、騙されたと思って「とにかく書いて」みてください。
あなたは「自分が思った以上に書けること」にびっくりするでしょう。ただ、ここで調子乗ったらいけません、常に謙虚な姿勢は大切です。
文章を書くのが苦手な人にやってほしいことの1つ目は「考えるより書くこと」です。
「書く」ではなく「伝える」

文章を書くのが苦手な人にやってほしいことの2つ目は「「書く」ではなく「伝える」」です。
あなたが文章に苦手意識がある理由の1つが「書こう」と思っているからです。
「え!文章って書くものではないの?」
実は文章は書くものではありません。
文章とは「伝える」ものです。
「伝える」という目的で文章を書いていくと自然と手が進むでしょう。
これは、あなた自身がいつも証明していることです。
たとえば、誰もが毎日LINEやメールで文章を書いています。
ただ、ブログを書こう、Twitterでバズを狙おう、などと思って手が止まってしまいます。
なぜなら、LINEもメールも誰かに何かを「伝えよう」とするから書けるのです。
つまり、文章を「書こう」と思うと書けない、文章を「伝えよう」と思うと書けます。
書こうとすればするほど書けないって残酷ですよね。多くの人は自分の中から文章を生み出そうとしていますが、そもそも自分の中から生み出そうというのが間違いです。
「自分」ではなく「相手」から文章を考えると、文章をすらすら書くことができるでしょう。
では、「書こう」としてはいけないのか?
そんなことはありません。自分の文章ですので自分のため書いても問題ありません。
ただ、誰かに読んでほしい場合、少しは「伝える」を意識すると良いです。
書くスピードを上げる

文章を書くのが苦手な人にやってほしいことの3つ目は「書くスピードを上げる」です。
これは文章を書くときに「パソコン」か「スマホ」か「鉛筆など」によって分かれますが、今回は「パソコン」を例にしてお伝えします。
パソコンで文章の書くスピードを上げるというと、「タイピングの速度を上げる」です。
この「タイピング速度」が「文章を書くのが苦手な人」にとってかなり大きな役割を果たします。なぜなら、タイピングが早くなることでメリットがあるからです。
メリットを話す前に、タイピングが遅いデメリットをお伝えします。
タイピングが遅いデメリット
集中力が低下する
1つ目は「集中力が低下する」です。
タイピングするたびに「キーボードを確認する作業」が入ります。たとえば、キーボードを見るために下を向いて姿勢が悪くなる、文章を使う頭と正しいキーを探す頭が共闘する、ということが起きてしまいます。
作業効率が落ちる
2つ目は「作業効率が落ちる」です。
キーボードを見ながらタイピングをしていると作業効率が落ちます。シンプルに「タイピングが速い人」の方が文章を作成するスピードが早いのは明白であるからです。
おそらく、タイピングが速い人と遅い人では文章を作成速度は2倍〜4倍は違うと思います。
タイピングのメリット
タイピングのメリットはデメリットの反対で、「集中力が上がる」「作業効率上がる」です。そして、あと1つ大きなメリットがあります。
それは「小さな自信がつく」です。
タイピングが速くなると少し自信になります。
文章を書くのが苦手な人は、「文章を書くのに自信がないから苦手」なわけです。
つまり、タイピングをして自信をつければ、必然的に文章が苦手ではなくなります。
「屁理屈だ」「自信がつくのと文章力は関係ない」
屁理屈かもしれません。
もちろん、いくらタイピングが速くなったからといって、いきなり村上春樹にはなれません。
ただ、重要なのは「文章を書く」という苦手意識をなくすことです。
タイピングを鍛えることで、確実に文章を書くという苦手意識をなくすことができます。
つまり、タイピング速度を上げることが「文章を上手くなるための一歩」となります。
とはいえ、天才級にまでなる必要はありません。寿司打というタイピングツールで高級コースができれば問題ないと思います。
詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
「タイピング」も「ランニング」も同じです。速い人の方が目的地に早く到達します。
騙されたと思って、タイピングを極めてみてください。
あなたの文章を書くという苦手意識はなくなります。
書かないといけない状況を作る

今回は「文章を書くのが苦手な人にやってほしい3つこと」ということでお伝えしましや。
まとめると、
- 1つ目にやってほしいことは「考えるより書くこと」で、「何を書くかというアイデアは考えているときにではなく、書いているときに生まれるものであるから」ということです。
- 2つ目は「「書く」ではなく「伝える」」です。これは文章を「書こう」と思うと書けない、文章を「伝えよう」と思うと書ける、ということです。
- 3つ目は「書くスピードを上げる」です。パソコンの場合はタイピング速度を上げることです。タイピングが速いと「集中力が上がる」「作業効率上がる」さらに「少し自信がつく」というメリットがあるからです。
今回お伝えした3つことを行えば、確実に「文章が苦手」から「文章が得意」へとなるでしょう。
書かないといけない状況を作る
最後に、文章を書くのが苦手から克服した私から「書かないといけない状況を作る」ということで2つお伝えします。
宣言する
1つ目は「宣言する」です。
新年の目標、がんばっていますか?
こんなことはさておき。
何かを継続したいとなったら「やらざるおえない環境に入る」ことが重要です。
なぜなら、人の意思は弱いからです。
たとえば、「3ヶ月後に5キロダイエットする!」と決めて「食事制限」や「運動」をしようとしても継続できません。
人の意思だけでは、達成は難しいでしょう。
「文書を書くのがうまくなりたい!」と思うのなら「書かないといけない状況を作る」ことが大切となります。
そのためにも「誰かに宣言する」ことをおすすめします。
誰かに宣言することで「自分」だけではなく「他人」を巻き込むことができます。実際には巻き込むというよりは「監視」の役目です。
「友人に自信持って宣言したからにはやる」「SNSで目標を発疹したからやる」こんな気持ちになれるでしょう。
やはり、他人の圧力は強いです。人間は誰かから影響を受けることが多いです。
こうすることで「書かないといけない状況」になり、あなたの文章力はうまくなります。
ちなみに「誰かと一緒にやる」ということが可能であれば、こちらの方が効果的です。一緒に早起きをする、一緒に副業を始める、でもなんでも良いです。
1人ではがんばれなくても、誰かとなら頑張れるのです。
ほんとうにやらないとやばい状況を作る
2つ目は「ほんとうにやらないとやばい状況を作る」です。
この方法はほんとうにおすすめしません。絶対にしないでください。
これはもうポケモンでいう「はかいこうせん」です。
3つのステップがあります。
- 大きな変化をして人生を変える
- それによる反動を受け、ひたすら耐える
- 絶望的な状況から脱する
まずは、大きな変化を起こします。たとえば、「副収入と貯金がなく会社をやめる」「すべての関係を断つ」「日本を捨てる」などです。
これらの大きな変化は自分を変える反面、後に大きな反動を受けます。
たとえば、「勢いで会社をやめてしまったことを絶望する」「恋人や友人との関係がなくなる」「海外怖い」などです。
そして、このような状況から這い上がる力、つまり「ほんとうにやらないとやばい状況」です。
正直、これを意図的にした人は、もう何も心配は入りません。
確実にうまくできるでしょう。
私がこの方法を使うとしたら、最後の賭けです。どんなにがんばっても何も成果が出なかったらこの方法をします。
命がけの方法ということで「わるあがき戦法」と名付けます。
ということで今回は以上となります。
【文章の書き方!】これだけ覚えれば文章はうまく書ける
「文章を書くのが苦手」
「文章をうまく書けない」
「文章をすらすら書く方法はないのかな?」
ここでは「【文章の書き方!】これだけ覚えれば文章はうまく書ける」ということでお伝えしたいと思います。
「文章を書くのが苦手」「文章をうまく書けない」「文章をすらすら書けない」という方に共通していることがあります。
それは「文章の型を知らない」ということです。
逆にいうと「文章の型」を知ることができれば、文章をうまく書くことはできます。
これから文章の型を3つ紹介します。
PREP法
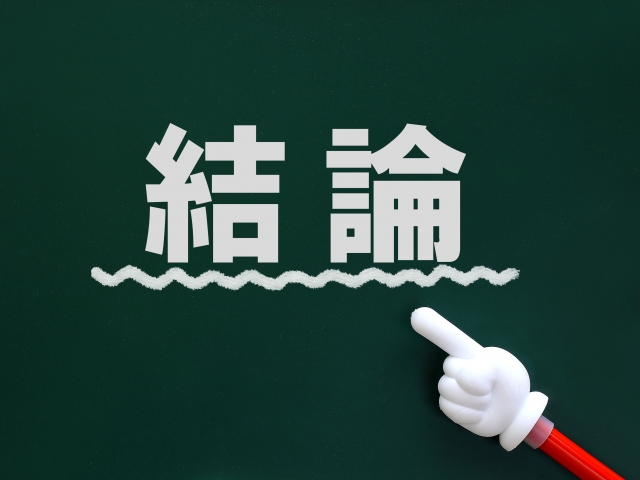
PREP(プレップ)とは「Point・Reason・Example・Point」の略です。
- 「Point」→ポイント・結論
- 「Reason」→理由
- 「Example」→具体例・実例・事例
- 「Point」→繰り返しポイント・結論
このような順番で文章を構成していきます。
PREP法の型を使えば「わかりやすい文章」書くことができます。なぜなら、結論重視であるため文章に説得力を感じるからです。
もっと具体的にPREP法を解説します。
「Point」→ポイント・結論
PREP法を使うことであなたの文章力はアップします(最初に文章の結論)。
「Reason」→理由
なぜなら、PREP法は相手にわかりやすく伝える文章であるからです(結論に対する理由)。
「Example」→具体例・事例。実例
PREP法は「結論→理由→具体例→結論」という結論重視であるため、読みやすい文章となります(理由を裏付けするような具体例・実例・事例を挙げる)。
「Point」→繰り返しポイント・結論
以上から、PREP法を使うことであなたの文章力は上がります(最後に、ポイント。結論を繰り返し述べて、全体のまとめを)。
と、このような感じです。
この例は少し簡潔すぎて、甘い部分もありますが、このような感じで書いていけば文章力はアップします。
また、PREP法の型に文章を入れるのはかんたんです。
かんたんであるのに「わかりやすい文章」となるため、ぜひ活用してみてください。
ぶっちゃけると「PREP法」さえ覚えていただければ問題ないと思います。
このあとに文章の型を2つお伝えしますが、もっとも覚えてほしいのは「PREP法」です。
とはいえ、世界は結論重視ではありませんので、残りの2つもぜひ参考にしてみてください。
序論→本論→結論

「序論→本論→結論」これに何か名前があるのかわかりませんが、結構使われていると思います。
序論、本論、結論の3段構成となります。
- 「序論」→どのような文章で、誰に向けて書くのか、文書の前提となる部分
- 「本論」→序論で示した主張に説得力を出すために、データや具体例を出して正確にする
- 「結論」→最後のまとめの部分、主張を簡潔にして1番伝えたいことを示す
このような順番で文章を構成していきます。
序論→本論→結論の型を使えば「伝えたいことをより正確に」書くことができます。なぜなら、文章の主張が明確に説明できるからです。
もっと具体的に序論→本論→結論の型を解説します。
序論
これからの世の中で「文章力」は確実に必要になります。
インターネットの普及によって、誰もが文字を書いて発信できる時代となりましたXやInstagram、ネット記事などを誰もがみたことはあるでしょう。
そんな時代において「あること」が判明しました。それが「文章力の低さ」です。
たとえば、「ユニクロでいいや」とXに書いてあったらどう思いますか?
「ユニクロ良いよね」という人もいれば「ユニクロでいいってユニクロを舐めているのか」という人もいます。
これの原因は「人によって文章を受け取り方が違う」からです。これが原因で「炎上する人」も出てきます。また、誰かを誹謗中傷して亡くなることもあります。
そのため、私たちは「文章力」を学ぶ必要があります。誰もが自由に発言できるからこそ、文章力を学ぶことで他の人よりも価値のある人材になれるのです。
本論
では、「文章力」をアップさせるためには具体的にどのようにして学べば良いでしょうか?
文章力をアップには、「読解力」「論理力」「注意力」3つの力が必要となります。
たとえば、「読解力」とは文章を読み解く力のことです。読解力がないと文章を間違って認識して誤解をうむ可能性があります。これからの時代は「相手の言いたいことや気持ちを理解できる」力が必要となります。それが「読解力」です。
実際に現代人は「読解力」が低いと言われています。
読解力を鍛えるためには「相手の背景を知る」「読書をする」「人と多く話をする」この3つです。
これらの3つを鍛えることで「読解力」が身について「文章力」アップにつながるでしょう。
起承転結
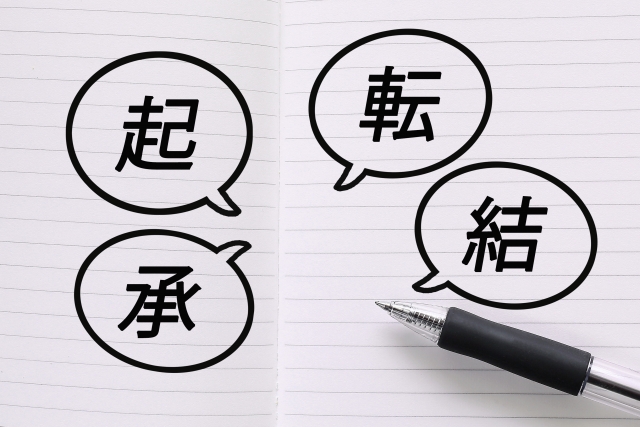
起承転結は小説などでよく目にする構成だと思います。文章全体が起承転結の4つで分かれています。
これは主張したい内容に向かって相手の興味関心を少しずつ喚起していく構成であるため、じっくりと読んでほしい文章を書くときに適しています。
- 「起」→これから読むにあたって知ってほしい前提の知識や情報をまとめる
- 「承」→「起」で提示した知識や情報を詳しく解説する、「転」つなげる役目
- 「転」→「承」で深めた知識や情報を元に主張したい内容や主題を書く、畳みかける
- 「結」→これまでの内容をまとめる、最後の締め括り
起承転結の構成は日本語によく見られる構成であるため、日本人にとって読みやすいものとなります。
では、具体的に「ドラえもん」を例にして起承転結の型に入れてみます。
「起」
困ったことが起きて、のび太はドラえもんに「道具を出して」とお願いする
「承」
ドラえもんの道具を使ってのび太が調子に乗る
「転」
何かトラブルが発生して流れが変わる
「結」
のび太がドラえもんに助けを求めて問題を解決してくれる
と、このような感じになります。
ドラえもんを例にすると結構わかりやすいですよね。のび太がドラえもんの道具を使ってトラブルを起こし、そのトラブルが解決されて物語がおわります。
ドラえもんの他にもアンパンマンや桃太郎、RPG作品、ラブコメなど様々なものに起承転結が使われています。
私たちが起承転結をよく目にする理由には、子どもの頃からあらゆるストーリーに起承転結が使われていたからと思いました。いわゆる王道作品です。
起承転結は、日本人にとっては読みやすい反面、結論があとになるため、文章を読み切るまで相手の興味関心を喚起し続ける必要があります。
しっかり書こうとしたらかなり難しい構成です。人気の小説やアニメ、映画などは上手く作られています。
とはいえ、たしかに読みやすいので、おすすめの構成となります。
型にとらわれすぎないようにしよう
今回は「文章の型!これだけ覚えれば問題なし」ということで3つの文章の型をお伝えしました。
- PREP法
- 序論→本論→結論
- 起承転結
今回お伝えした3つ方法は、あなたの文章力をアップさせるために役立つでしょう。
ただ、注意してほしいことがあります。
文章の型に捉われすぎると「視野が狭くなる」可能性があります。そのため、どのような構成であれば伝わりやすいのか、読み手を常に思い浮かべて書くと良いでしょう。
文章の型は確実にあなたの文書力を高めてくれます。
ぜひ取り入れてみてください!
わかりやすい文章を書く3つのコツ
「文章を書くのが苦手」
「文章がわかりづらいと言われる」
「わかりやすい文章を書くコツが知りたい」
こんな疑問に答えます。
ここでは「わかりやすい文章を書くコツ」ということでお伝えしたいと思います。
あなたの悩みは解決できます。
わかりやすい文章とは

仕事やコミュニケーションで何かを伝えるときは「明確でわかりやすいこと」を重要視されます。
なぜなら、ビジネスではシンプルに素早く伝えることが重要だからです。
たとえば、上司に何か用件を伝えるとき、Aさんは「〇〇部長、この間の件ですが、こんな感じになっておりまして、こことここが深く追及できずにいるので何かアドバイスいただいてもよろしいでしょうか?」と伝えました。
一方、Bさんは「〇〇部長、〇〇の件ですが、アドバイスをいただけないでしょうか?こことここについて意見をいただけたらと思います」と伝えました。
AさんとBさん、どちらの方がわかりやすく伝えられていますか?
B さんですよね。
Aさんのどこがダメだったかというと2つあります。
1つ目は「この間の件」って「いつだよ」となってしまいます。上司は忙しいです、この間の件といってもいつのことなのか瞬時に思い出すことはできません。
これは「相手の立場でものごとを考えることができていない」の定型例です。
2つ目は「こんな感じになっておりまして、こことここが深く追及できずにいるので何かアドバイスいただいてもよろしいでしょうか?」ではなく「まずは相手に何をして欲しいのか」を伝えた方がわかりやすいです。
この場合は、まず「アドバイスが欲しい」と伝えることで上司は「ああ、アドバイスが欲しいのか」と考えてくれます。
ということで今回は「わかりやすい文章」を書くコツを3つ紹介します。
わかりやすい文章を書くことで「仕事で評価されて出世する」「自分の事業が波に乗って成功する」「円滑な人間関係を築ける」といったことができるでしょう。
結論を最初に
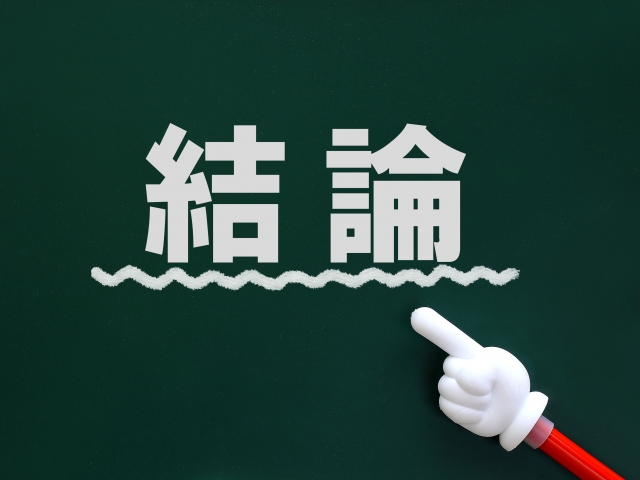
ビジネスにおいて「結論を最初に書く」は鉄則です。
なぜなら、簡潔に素早く伝えなければいけないからです。
先ほど、上司に何か用件を伝えるときの例と同じです。Aさんは「相手の立場でものごとを考える」「最初に何をしてほしいのかを伝える」が抜けていました。
まずは、相手に伝えたい結論を最優先で書くと良いです。
「理由→結論」ではなく「結論→理由」というのを意識すると良いでしょう。
結論を最初に書くことで、ムダのない円滑なコミュニケーションを送れるようになります。
ただ、1つ勘違いして欲しくないことがあります。これは雑談を禁止するというわけではありません。
たとえば、職場の人や取引先の人に対して、ムダのないコミュニケーションというのは返って逆効果になりえます。何か寂しく感じてしまうのでしょう。
上司と話しても用件だけ、部下と話しても用件だけ、取引先との交渉でも用件だけ、これでは人間関係は構築できません。
ムダのない円滑なコミュニケーションというのは「何か伝えないといけないことがある」場合です。
1文を短く
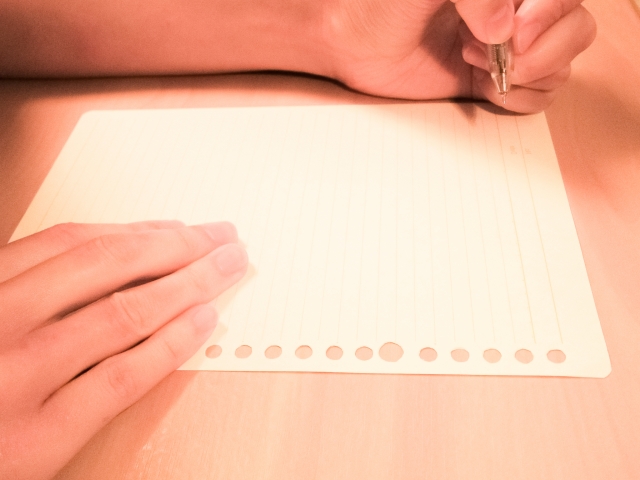
1つの文が長すぎると、「読みにくい」「伝えたい内容がぼやける」といったことが起こります。
たとえば、
「わかりやすい文章は相手に負担を与えることがなく素早く簡潔に伝える必要がありますがそのためには結論を最初に書いて1文を短くすることが大切であり、相手が話の内容を想像できるようにメンタルモデルを形成させることであなたは仕事で評価される人になるでしょう」
この文章はどうでしょうか?
「読みにくい」「伝えたい内容が分かりにくい」ですよね。
1文は「最低でも50文字以内」がベストです。
先ほどの例は120文字超える長文でした。
では、分かりやすい例をみてみましょう。
「わかりやすい文章を書くためには「素早く簡潔」に伝える必要があります。なぜなら、相手に負担を与えないからです。
そのためには、「結論を最初に示す」「1文を短くする」「相手に内容を想像させるためにメンタルモデルを形成する」が大切となります。
これらの3つを行うことで、あなたは仕事で評価されるでしょう。」
何かポイントがあるとしたら、「句読点を活用する」「文末を変化させる」「変な言い回しをしない」ここらへんを意識すれば問題ないでしょう。
まとめると、1文が長い文章は、相手に負担をかけてしまうため「最低50文字以内」の文章を目指すと良いです。
メンタルモデルを意識しよう

先ほど「メンタルモデル」という用語が出ていました、説明がなく申し訳ありません。
読んでいて、何だろうと思った人もいるでしょう。
メンタルモデルとは「人が何かしらの情報に対して持っている仮説」のことです。
たとえば、誰もが「ライオンやクマは危険」という情報を持っています。この情報を持っている人は、ライオンやクマに遭遇したときは反射的に逃げるでしょう。
これがメンタルモデルを形成した結果です。
ライオンやクマに対するメンタルモデルを形成していない人や違うメンタルモデルを持っている人は、逃げるなどの反応はしません。
これがどうしてわかりやすい文章を書くために必要なのか?
それは「相手に文章の展開を予測してもらう」ためです。
たとえば、「これから〇〇のポイントを3つお伝えします」となれば「あ、ポイントが3つあるのか」となります。
何を伝えたいのかわからない文章は、読んでいて負担ありますよね。
まとめると、メンタルモデルを形成させることで、相手は文章の展開を予測して読めるため、相手に負担がないわかりやすい文章となります。
とはいえ、これはビジネスなど円滑なコミュニケーションが必要な場合です。小説や映画などのエンタメ作品の中には、次の展開がわからない方が良いものもあります。
必要に応じて、メンタルモデルを活用してみてください。
文章は読み返そう

今回は、「わかりやすい文章を書くコツ」ということで3つお伝えしました。
- 1つ目は「結論を最初に」素早く簡潔に伝える
- 2つ目は「1文を短くする」1文は50文字以内がベスト
- 3つ目は「メンタルモデルを意識する」相手に文章の展開を予測させる
今回紹介した以外にも、わかりやすい文章を書くコツはたくさんあります。
もっと知りたい方は本やインターネット等で調べてみてください。
最後にWebライターである私から「文章は読み返そう」ということで2つお伝えします。あくまでも1つの意見です。
文章は1回では完成しない
1つ目は「文章は1回では完成しない」です。
文章は何度も「修正を繰り返す」ことでより良くなっていきます。
修正することで「もっと良い言葉や言い回し」が見えてくるでしょう。
あなたも「仕事でメールを送る前や報告書を提出する前」「友人にメッセージを書いたあと」は読み返すことはあると思います。
私は文章を書くときは、まずは「ひたすら書くこと」を意識しています。
そして書いたあと、また読み返して、誤字や脱字のチェックはもちろん「もっと改善できないか」と思っています。
文章を読み返すことで、より磨きがかかります。
この間、ある本に「文章は最初に書いたものこそ素晴らしい」と言っていました。
たしかに、最初にズバッと書いた文章って気持ち良くて、良いものだと思います。これも1つの意見であると思って受け止めました。
ただ、文章がつたない私にとっては「文章を読み返す」は文章をより良くできる最強の行動です。
文章に自信のない方はぜひ読み返すことをおすすめします。新しい発見が見えてくるかもしれません。
学びがある
2つ目は「学びがある」です。
文章を読み返すとどうして学びがあるのか?
それは「昔の自分を見ることができるから」です。
これは日記やブログを書いている人、もしくは、小学生や中学生の頃に卒業文章を書いた人はわかるかもしれませんが。
昔に書いた自分の文章って妙に恥ずかしくありませんか?
「ああ、昔の自分はこんなことを考えていたのか」「昔はこんな夢を持っていたな」「何か痛いことを書いていたな」などと。
恥ずかしい反面、読み返していると「学び」があります。
たとえば、「昔の自分の文章から今の文章に磨きをかけるヒントを得ることができた」「昔の自分の思いを知ることで前を向けて頑張れるようになった」など、良いことだらけです。
もちろん、その文章を読み返すことで「かならず今の自分が変わる」とは言いません。
実際に自分の根本を変えることは難しいです。
元々ネガティブだった人はポジティブにしようと思っても、さらにネガティブになる可能性もあります。
私はポジティブに考えれば挑戦できるという理想論は意味がないと思っています。
今の自分は変わらないにせよ、何かしたのヒントを得ることはできると思っています。
人に読まれる文章を書く3つのコツ
「文章を書くのが苦手」
「企画を立てるときいつも失敗する」
「何か人に読まれる文章を知りたい」
ここでは「人に読まれる文章を書く3つのコツ」ということでお伝えしたいと思います。
人に読まれる文章とは

そもそも人に読まれる文章とは何でしょうか?
最初に人に読まれる文章について整理しておきます。
経済は人がいるからこそ成り立ちます。誰かがモノを売って、それを求めて購入する人がいるから経済が周ります。
人に読まれる文章も同じです。誰かが文章を書いて、それを読む人がいます。
では、人に読まれる文章の特徴とは何でしょうか?
たとえば、あなたが企画を立てるのに苦戦しているとき、書店で「絶対決まる!企画の立て方」というタイトルの本があったとしましょう。
あなたをその本を手にとりますか?それとも素通りしますか?
そんなタイトルの本があったら手にとって読みますよね。
どうして手にとって読むのでしょうか?
それは「自分の悩みを解決してくれそうだから」です。
つまり、人に読まれる文章とは「自分がいま考えていることと一致したとき」です。
今回の場合は、あなたは企画を立てることについて「悩んで」いました。
そして、本を手にとって理由は「いまの自分に関係がありそうだったから」ということです。
では、具体的にどのようにして文章を書けば良いのか?
人に読まれる文章を書くためにはたくさんコツがありますが、今回は3つに絞ってお伝えします。
文章を書く目的を決める

1つ目のコツは、文章を書くときは「目的を決める」と良いです。
なぜなら、文章を書く目的を書かないと「内容がぶれてしまうから」です。
「そんなの当たり前だろう」という声が聞こえてきます。
ただ、意外と意識しないとずれることがあります。
目的を明確にするにあたって、2つポイントがあります。
目的を意識する
1つ目は「目的を意識する」です。
たとえば、「戦後の日本はどのようにして経済を発展させてきたのか3000文字で書きなさい」という内容があるとします。
まあ、普通に調べながら書いていくと思います。
ただ、最初は「戦後から現在までの年表を順に書けば良い」と思っていますが、いつの間にか「戦後に起きた重要なことしか書いていない」となることがあります。
こうなる原因は「目的を意識していないから」です。
あなたも、あるテーマについて書くことがある際に「いつの間にか少し内容がずれていた」なんてことありません?
とはいえ、そもそも目的を立てないということもあるかもしれません。
ただ、目的を決めて書かないと内容がトンチンカンなことになってしまいます。
結果を想定する
2つ目は「結果を想定する」です。
たとえば、「仕事で〇〇について相談したい」というメールを書くとします。
普通に内容に相談事項を書くと思います。
ただ、ここでだらだらと前置きが入ると、何を伝えたいのかがぼやけてしまいます。
この場合ですと、件名で目的を示すと良いでしょう。「【相談】〇〇について」と、このように書くと明確でわかりやすいですよね。
やはり、目的のない文章は読み手に負担をかけてしまいます。そうならないように、相手に何をしてほしいのかを「明確」にさせることが大切です。
このように、人に文章を読んでほしいのなら「目的を決める」が大切です。そのためには「目的を意識する」「結果を想定する」この2つがポイントとなります。
相手目線で書く

2つ目のコツは、文章を書くとき「相手目線で書く」です。
なぜなら、「自分目線で文書を書いてはいけない」からです。
「自分の文章なのに自分目線で書いてはいけないってどうゆうこと?」と思われるでしょう。前提として、人に読まれる文章を書きたい場合です。
相手目線で文章を書くにあたって、大切なことは「どう伝えるか?」ではなく「どう伝わるか?」を考えることです。
なぜなら、前者は主役が自分で、後者は「主役が相手」となるからです。
たとえば、あなたが「確定申告の書き方」というテーマでブログを執筆したとします。ずらっとたくさん書くと思いますが、ここで忘れていけないことは「相手は何も知らない」ということです。
最終的なゴールは「確定申告の書き方をわかって実際に書いてもらうこと」ですよね。
それなのに「専門的な用語」や「具体的なステップを書かない細部にわたって書かない」というふうにしてしまうと、相手は「内容がわからない」と思って、読んでくれなくなります。
よく「小学生にもわかる文章を書きなさい」というふうに言われます。まさに、その通りです。
「相手に目線」で文章を書くと、人に読まれる文章を書けるようになるでしょう。
文章を一気に書こうとしない
ここまで文章を書くときは「目的を明確にする」「相手目線で」と言いました。
実際どうでしょうか?実践できそうですか?
ぶっちゃけると難しいと思います。
私はこんな偉そうに語っていますが、できていない部分がたくさんあります。
とくに、「書くことに苦手意識がある人」や「文章を書こうと思うと気が重い人」にとってはとても難しいと思います。
これはコツと言わないかもしれませんが「文章を一気に書こうとしない」ということを根底においた方が良いです。
なぜなら、「一気にすべてのことを詰め込むとパニックになるから」です。
いきなり「目的を明確にして、相手目線で書きなさい」と言われても難しいです。何百回も練習して始めて身につくものです。
また、そもそも「1回で文章は完成しないから」です。
一回で文章の構成を決める、一回で構成の中身を書く、というのはほとんどできないからです。
本の著者さんは出版社さんと打ち合わせをしたりして、何回も文章を修正しています。
1つずつ練習を重ねていけば、あなたの文章は輝き出すのです。
毎日3000文字を生み出す3つのコツ
「ブログを毎日投稿したいけど、書くネタが思いつかない」
「毎日3000文字も書けない」
「何か毎日3000文字書けるコツないかな?」
こんな疑問に答えます。
ここでは「毎日3000文字を生み出す3つのコツ」というテーマでお伝えします。
この記事を見ているということは、あなたは「文章を生み出したい」と思っています。
そして、「何か役立つことはないかな?」「せめて少しでも何か現状を良くする情報を知りたい」こんなふうに考えているでしょう。
文章を生み出すって難しいですよね。
私は今でこそ、毎日3000文字書いていますが、少し前までは1週間に3000文字を書けるぐらいのレベルでした。
毎日「何を書こうかな?」とずっと悩んでいました。
そんな私がどうして毎日3000文字以上の文章を書くことができるようになったのか?
それは「書く内容を人の頭を使って探したから」です。つまり、自分で書く内容を考える必要はないのです。
たとえば、「ネットニュース等で話題になっていることを自分なりに解釈してみる」「偉人や有名人の言葉を引用して自分の意見を書いてみる」「本の書評をする」などです。
このように、自分がゼロから生み出すのではなく、すでにある内容を自分の言葉で書いていけば、無限に書く内容が生まれてきます。
「いいたいことはわかるけど、そもそも自分の言葉で書くのが難しい」
たしかに、その通りです。
そこで、今回は「毎日3000文字を生み出す3つのコツ」ということで、自分の言葉で書けるようになる方法を3つお伝えします。
これからお伝えする3つのことを取り組むことができれば、毎日3000文字どころか5000文字、10000文字も到達できます。
この記事で、あなたの悩みが解決したら嬉しい限りです。
大前提!時間を確保する

まず、最初に何よりも大事なことがあります。
それは「時間を確保」しないと3000文字を生み出すコツを知っても意味ない、ということです。
具体的にどのくらいの時間を確保すればいいのか?
人によって差はありますが、最初は「3時間」くらいが妥当かなと思います。というのも、大体1時間で1000文字を書く計算です。
3時間確保できれば、このあとに紹介する3つのコツと合わせることで、もう確実に毎日3000文字は突破できます。
ただ、「3時間なんて確保できないよ」「時間を減らすことが難しい」という方いると思うので、もっと時間を短縮できる方法を2つお伝えします。
文章の型を使用する
時間を短縮できる方法の1つ目は「文章の型を使用する」です。
具体的にはこちらの記事を読んでほしいです。
ここでは、かんたんに説明します。
文字をゼロから考えるのは大変ですよね。いざ文章を書くとき「どのように文章を書いていけばいいのかわからない」となります。
それを解決してくれるのが「文章の型を使用する」です。世の中には様々な文章のテンプレートがあります。
文章のテンプレート、つまり「すでに出来上がった型」に書く言葉を入れることで、時間を短縮が可能となります。
ムダな思考時間を減らす
時間を短縮できる方法の2つ目は「ムダな思考時間を減らす」です。
「ムダな時間を減らせ!」
これはいろいろなビジネス書などで書いています。知っている方も多いかと思います。
たしかに、理屈ではわかりますよね、「ムダな時間を減らせばその分時間も増える」と。
ただ、実践となると、なかなか難しいと思います。
ただ、はっきりいいますと、現状の生活の中で「時間を増やす」となると何かの「時間を減らす」必要が出てきます。
あなたの今の生活でムダな時間はどこか?聞かれたら答えることができますか?
「朝はゴロゴロしてしまう」「仕事から帰ったあとはソファーでくつろいでテレビを見る」「ついゲームをする」「SNSをだらだらと見る」「動画を観る」などとあるかもしれません。
あなたの日常生活の中には「時間を減らす」ポイントはあります。
先ほど挙げたことや「仕事から帰宅時間が遅くても、朝は時間がある」「通勤時間や食事時間」など、きっと見つかるはずです。
例外として、朝から晩まで忙しい超スーパービジネスマンを除いて、
それでも、時間を作れない方は「ムダな時間を減らす」のではなく「ムダな思考時間を減らす」こちらに切り替えると良いです。
屁理屈ですが、どうしてもという方は参考にしてみてください。
「ムダな思考時間を減らす」とは、ムダな時間にムダな思考をしないということです。
これの何がいいかというと「ムダな時間をすべて、ムダではない時間に変える」ことができるからです。
たとえば、はじめしゃちょーの「世界最大級のグミを1人で食う!」という動画があります。一見、グミを食べるだけの動画で、ムダな時間を過ごしていると思います。
ただ、驚くべきことにこの動画は1億再生しています。謎ですよね、みていないという方はぜひ。
ここで大切なことが「なぜ1億再生いったのか?」を考えることで「ムダな時間」が「意味のある時間」になります。
そして、ここで考えたことが3000文字を生み出すネタになることもあります。
この方法は「すべてのことを意味のあるもの」にするという究極の思考となります。
以上です。「時間を確保する」という内容が思った以上に膨らんでしまいましたが、これから「毎日3000文字を生み出す3つのコツ」をお伝えします。
本を読む
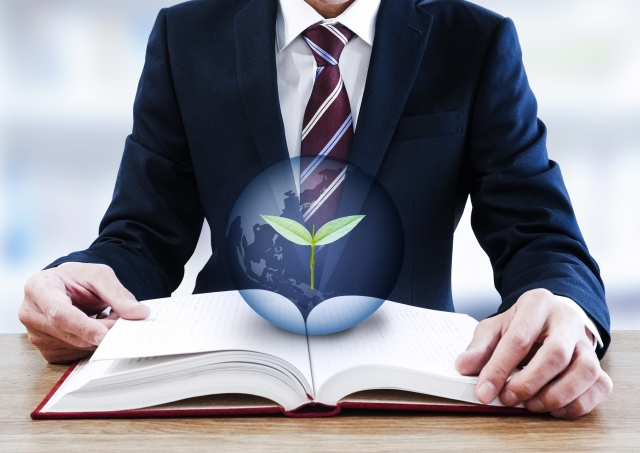
「読んだ本の数ほど文章がずっしりする」
毎日3000文字を生み出すコツ1つ目は「本を読む」です。
3000文字を生み出すためには「インプット」が必要となります。いくら3000文字書こうと思っても自分の中に「言葉」がなければ書けません。
「本を読むといっても具体的にどのような本を読めばいいの?」
ひとまずは「自分の書こうとしている分野の本」を読むと良いです。順番として、1つ分野に詳しくなる、そしたら他の分野の本を読んでいく、この繰り返しです。
「幅広く読んではいけないの?」
いいえ、幅広く読んでも良いです。
ただ、効率的に学びたいのなら「まずは1つの分野」に集中です。
なぜなら、1つの分野に詳しくなると「他の分野を学ぶときに要領を掴みやすい」「強みができる」「自信になる」これらのメリットを得ることができるからです。
「自分の書きたい分野がわからない」という方もいるでしょう。
そんな方はまずは幅広く読んで、「気になる分野」「面白い分野」「楽しい分野」を見つけたら、その分野に集中すると良いです。
この「1点集中読み」のデメリットとして良くいわれるのが「様々な分野の本を読んだ方が刺激はあって良い」というものです。
これに関しては「そんなことない」と答えます。
なぜなら、世の中に刺激が溢れているからです。
たとえば、「心理学の分野を極める」となったときでも、仕事をしたり、テレビを見たり、誰かと話したりすると思います。すでにそこから刺激をもらっています。
学びの最初は「肩身が狭い」です。ほとんどの人は、とくに何かに詳しいわけでもなく、特別スキルを持っているわけでもありません。
また、本の話に戻りますが、これから本を読む最大の理由をお伝えします。
それは「自分で考える力を身につけることができる」からです。
世間的には本を読むことは「情報や知識を得るもの」と思われています。ただ、本を読む本当の価値は「自分で考える力を得る」です。
もちろん良い本は情報や知識が体系的にまとめられているため、効率的に学ぶことができます。ただ、それ以上に「自分で考える力」というのが魅力的です。
いまは、世の中に情報が溢れすぎています。何が正解で不正解なのかわかりません。
そもそも正解も不正解もあるのかわかりません。また、とくに自己啓発系は本によってはもう矛盾ばかりするものもあります。
こんな世の中だからこそ「自分で考える」ことで「自分の選んだ道を正解にする」が大切となります。
「本を読む」は私の得意分野でもあるため、熱く語りました。
毎日3000文字を生み出すコツの1つ目は「本を読んで書きたい分野を極める」です。今日から本を読みましょう!
「そもそも本を読む習慣がない」「本なんて読まない」という方はこちらの記事を読めば、読書を習慣化できます。
耳で学習をする
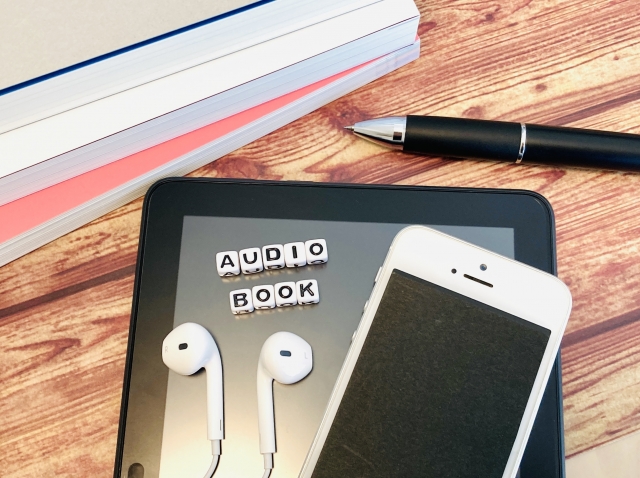
「目で見て学ぶことだけが学習ではない」
毎日3000文字を生み出すコツ2つ目は「耳で学習をする」です。
耳で学習すると聞くと、英語のリスニングなどがあります。
ここでいう耳で学習は「youtubeの書籍解説動画を聞く」「オーディオブックを聞く」「ためになるラジオを聞く」などです。
あなたは「イヤフォン」をつける習慣がありますか?
イヤフォンをつける習慣がある人もいればない人もいるでしょう。
ただ、毎日3000文字を生み出したいのなら「耳で学習をする」をしないと難しいです。なぜなら、目で見て学習するだけでは足りない可能性があるからです。
たとえば、週5日に9時〜18時まで仕事をしているサラリーマンで、通勤に1時間かかる人を例にお伝えします。
このスケジュールで動いている人は、仕事が9時間(お昼含む)、通勤2時間消費しています。
1日は24時間ですので、残りは13時間です。
そのうち、最低7時間は睡眠するとして、自由な時間が6時間あります。睡眠以外にも、朝ご飯や身支度、夜ご飯やお風呂等を含めると、自由に使用できるのは3時間くらいかと思います。
もちろん人によって差はあります。
「3時間もあれば3000文字書けそう」
たしかに、可能です。ただ、3時間すべてを使用できるわけではありません。
人によっては絶対にしている習慣もあるでしょう。また、インプットする時間もあります。
せいぜい抽出しても1時間くらいでしょう。
そうなると3000文字は厳しいと感じます。
では、どうしたら良いのか?
こたえはかんたんです、「耳が空いているとき」に「耳で学習してインプット」すれば良いです。
たとえば、通勤中の場合、座れたら本を読めば良いですが、座れないときは立って本を読むのは難しい人もいると思います。また、歩いているときも本を読むと危ないのです。
そうなると、もう「耳で学習する」しかありません。
毎日3000文字を生み出すコツの2つ目は「耳で学習する」です。
「目で見て学ぶことだけが学習」ではありません。
あなたの耳を活用しませんか?
最近は耳でもかなり学習できるコンテンツがあります。
良い言葉をメモに残す

毎日3000文字を生み出すコツの3つ目は「良い言葉をメモに残す」です。
本を読んでインプットした、耳で学習してインプットした、それだけでは不十分です。
正確には、インプットしたことを忘れなければ十分です。
ただ、インプットしたことを忘れる場合は「良い言葉をメモに残す」これをおすすめします。
私も実際にしていることで、本や耳で学習したことをIPhoneのメモ帳にメモをしています。そして、ブログや電子書籍を書くときは、そのメモ帳を参考にしながら執筆しています。
たとえば、本を読んで「パブロ・ピカソは新しいこと挑戦する勇気がいかに大切かをきちんと理解していた。ピカソはこう言っている。「何を描きたいかは書き始めてみなければわからない」と」という内容が書いていました。
この言葉を文章にどのように活用するのかというと、「新しいことを挑戦したい」という人へ「自分が何をしたいのかはやってみないとわからない」と書けることができます。
また、著名人や著名作の引用は「権威性」があるので、自分が何者でもなくても、読み手に納得させる文章を書くことができるのです。
あなたは本で読んだことなど、インプットしたことを覚えていられますか?
毎日3000文字を生み出すコツの3つ目「良い言葉をメモに残す」です。
これを癖にしていれば、あらゆる知識を自分のものにできます。
片手間でできるのでぜひ行ってみてください。
とにかく書こう

今回は「【裏技】毎日3000文字を生み出す3つのコツ」ということでお伝えしました。
大前提は「時間を確保」するです。そもそも時間を確保しないと3000文字を生み出すことはできません。ムダな時間を減らすことが難しい方は「文章の型を使用する」「ムダな思考時間をしない」の2つをおすすめしています。
毎日3000文字を生み出すコツ
1つ目は「本を読む」です。インプットしなければアウトプットできません。
2つ目のコツは「耳で学習する」です。目で見て学ぶことだけが学習ではありません。あまり本を読む時間のない方、本を読む時間がある人にもおすすめしたいのが「耳で学習する」です。
3つ目のコツは「良い言葉をメモに残す」です。インプットして良いと思ったことをメモに残すことでブログに活用できるでしょう。
今回お伝えしたことをぜひ参考にして自分のものにしてみてください
とにかく書こう
最後に、毎日3000文字以上を生み出している私から「とにかく書こう」ということで2つお伝えします。
文章を書くのとスポーツは同じ
1つ目は「文章を書くのとスポーツは同じ」です。
たとえば、一般的に野球で上手くなろうとすると「バットを振る」「ボールを投げる」が重要になるでしょう。
バットをぜんぜん振らない、ボールをぜんぜん投げない、これで上手い人は「天才」か「武井壮のような自分の体の動かし方をマスターしている人」です。
天才やかなりの土台を持っている人以外は「とにかく練習」しないと上手くなるのは難しいです。
毎日3000文字以上を生み出したいと思っても、文章を書かなければ生み出すことはできません。いくら「本や音声でインプット」「メモを残す」などをしても。
「とにかく書く」これをしないと毎日3000文字はできないでしょう。
「とにかく書け」なんで突拍子もないことをいいましたが、最後に結果を出すのは「質」より「量」だと思っています。
つたない文章でも、誤字脱字のある文章でも、構いません。とにかく書いていれば、いずれ文章は上手くなります。
もちろん、それには「学び続ける」必要があります。
ぜひぜひ、今日から「文章をたくさん書いて、たくさん失敗」してください。
完璧主義は脱しよう
2つ目は「完璧主義は脱しよう」です。
これは、完璧主義をやめて「修正主義にしよう」ということです。
たとえば、上司に「あるプロジェクトの企画書を1週間後までにまとめてほしい」といわれたとしましょう。完璧主義の人は「1週間後に完璧な企画書」を提出します、一方完璧主義ではない人は「まずは仮説を立てて上司にすぐに」見せます。
どちらが、良い企画書を生み出せると思いますか?
結果はこうなるでしょう。
完璧主義の人は「上司に思ったのと違う」といわれてボツになる可能性が高いです。
完璧主義ではない人は、事前に企画書の方向性を上司に確認しているので「上司からこれで行こう!」となる可能性が高いです。
これ何が違うかというと、完璧主義の人は「一発で決めようとしている」、完璧主義ではない人は「修正を重ねている」ということです。
文章にも同じことがいえます。
たとえば、ブログを1記事書こうとする場合、完璧主義の人は「何週間も時間をかけて完璧にして書く」、完璧主義でない人は「まずは1回記事を書いて都度修正をする」になります。
これは完璧主義が悪いといっているわけではありません。完璧主義が良いときもあります。
要は「バランスを持った方が良い」ということです。
修正できるものは修正主義にして、出したら修正できないものは完璧主義にしようということです。
とはいえ、私は今でこそ毎日ブログを投稿して都度修正をしていますが、昔からそうだったわけではありません。
完璧ではない状態で「何かを世に出す」のは怖かったからです。
「笑われたらどうしよう」「下手じゃないかな?」と思っていました。
ただ、実際は修正もできますし、そもそもブログを訪れる人が少なかったので、「まあいいか」となりました。
完璧主義に悩んでいる人も多いでしょう。
悩みを解決するには「経験」が必要ですが、魔法の言葉を2つお伝えします。
「まあいいか」
「他人は思っている以上に自分に興味がない」
この2つの言葉をもとに、悩んでいる方は参考にしてみてください。