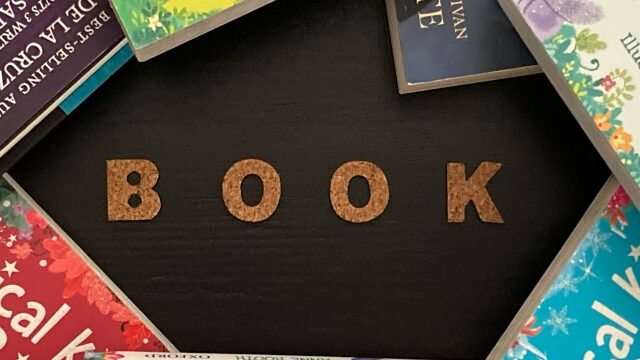【書評】スマホ脳(著者:アンデシュ・ハンセン)

「かもしれない」が人を動かす
「暇があるとスマホを触ってしまう方」
「やることがあるのについスマホを触ってしまう方」
「○○かもしれないと思ってスマホを触ってしまう方」
今回はアンデシュ・ハンセンさんが著者「スマホ脳」という本を書評していきます。
「なぜスティーブ・ジョブスは、我が子にiPadを触らせなかったのか」
という見出しが付いていて、かなりのインパクトがあります。
では、実際にどうしてなのか?
答えは本書に書いています。
さっそくお伝えしていきます。
著者のプロフィール
著者はアンデシュ・ハンセンさん。
1974年生まれ。スウェーデン・ストックホルム出身。前作『一流の頭脳』が人口1000万人のスウェーデンで60万部の大ベストセラーとなり、世界的人気を得た精神科医。名門カロリンスカ医科大学で医学を学び、ストックホルム商科大学でMBA(経営学修士)を取得。
※本の著者紹介ページ参照。
前作の「一流の頭脳」も読ませていただきました。一言でいうと、「運動すると頭が良くなる」という内容でした。本書でも運動について述べられています。精神科医さんが出す本は、エビデンスもしっかりあるので、おすすめです。
本のざっくりとした概要

本を読んで気になるのが、タイトルの「スマホ脳」です。
スマホ脳とは、「スマホに依存している状態」を言います。
著者は、「スマホに依存するな」と言います。
それはなぜなのか?
スマホはわたしたちに悪影響を与えるからです。
スマホによる悪影響がこちらです。
- ストレスを増加させる原因になる
- 睡眠不足を招く
- 集中力を低下させる
- 脳を刺激させて行動を誘う
- スマホを中毒になる
とはいっても、わたしたちはスマホを手に取っています。
自分の時間の使い方を思い出せば分かると思います。もうスマホを触りまくっているでしょう。
わたしも1日に6時間はスマホをいじっています。これは、「人生の3分の1」をスマホに費やしていることになります。
では、なぜスマホを触るのか?
本書でいろいろ説明していますが、とくに面白いと思ったことがあります。
それが、『「かもしれない」』です。
たとえば、X(旧Twitter)で投稿したとき、いいねが気になりますよね。ついついXを開いてしまいます。それはなぜか、いいねがついている「かもしれない」と気になるからです。
要は「期待感」です。本書では、ドーパミンを刺激すると言います。
- YouTubeを開くとき好きなチャンネルが投稿されている「かもしれない」
- XやYouTubeで人生を変えるような有益な情報がある「かもしれない」
- パチンコや宝くじが当たる「かもしれない」
わたしたちは、この「かもしれない」に影響されています。
期待感を刺激して、スマホ中毒、つまりは「スマホ脳」に誘っています。
これは、自分が悪いというよりは「人間の脳がそうできている」からです。逃げられません。
ただ、安心してください。
本書では、スマホ脳にならないための方法が書いています。
スマホ脳にならないため方法

運動をする
著者は、スマホを制限して「適切な運動」を推奨しています。
具体的には「週に3日45分ずつ」です。
なぜ、運動が良いのか?
それは、ストレスが軽減されて、集中力が上がるからです。
世界保健機関(WHO)によれば、運動やトレーニングをすることで「不安」身を守ることができると言います。
この「不安」を抱えることで、「ストレスが増加する」「集中できなくなる」といった症状が起きます。
あなたも、不安なときは常に気が張っていることもあると思います。
「不安」もまた、「かもしれない」を引き起こすタネであるでしょう。
運動は、そんなわたしたちを救ってくれる「予防」となります。
スマホ、とくにSNSを使わないこと
世界トップに影響力を持っている方々は「スマホを制限」しています。
- IPhone・iPadを生み出したスティーブ・ジョブズも、自分の子供のiPadのスクリーンタイムを厳しく制限している
- ビルゲイツは、子供が14歳になるまでスマホを持たせなかった
さらにフェイスブックの「いいね」機能を開発したジャスティン・ローゼンスタインは、インタビューでこう言います。
「ボタンをつくったことはFacebookのビジネスとしては良かったけど、ちょっとやりすぎな機能だったかもしれない」と。
わたしたちは、SNSの使い方を考え直さないといけません。
こんな方におすすめ!
- スマホに依存の生活をやめたい人
- 集中力を高めたい人
- ストレスを減らして、快適な日々を過ごしたい人
わたしは、本書に「人生をより良くする鍵」があると思っています。
その理由は3つあります。
・「かもしれない」は時間の無駄である
・運動でスマホ脳を対策。かつ運動は脳も身体も鍛えて健康になれる
・スマホ脳を対策して、自分のやりたいことを見つける
ぜひ購入して読んでみてください。
最後に

今回はアンデシュ・ハンセンさんが著者「スマホ脳」という本を書評しました。
本書で推奨している、「適度な運動」「スマホとの付き合い方」は、これから生きる人たちにとって「絶対に知らないといけないこと」だと思いました。
最後にひとつ話せていただきます。
本書では、スマホ脳をなくすには「適切な運動」が良いと言います。
本書でも触れている部分ではありますが、
スマホ脳にならないための方法は、やはり根本的なことは「やりたいことがない状態」だと考えます。
- どうして暇があるとスマホを触るのか?
- どうしてスマホで面白いことを探すのか?
- どうしてスマホが原因で心に不調をきたすのか?
すべては「やりたいことがない」からです。または「やらないといけないけど先延ばしにしている」とも言えます。
そうならないためにも、「これをしないといけない」「次にこれだ」と、やるべきことが常にある状態が最高かなと思います。
この記事が少しでもあなたの役に立てれば嬉しい限りです。