【書評】アウトプットする力(著者:齋藤孝)

「勉強してるのに成果が出ない」
「たくさんの本を読んでいるのに成果が出ない」
「何か良い方法ないのかな?」
今回は齋藤孝さんが著書「アウトプットする力」という本を参考にお伝えします。
齋藤孝さんは、教育学修士、明治大学教授、ベストセラー著作家などかなり多くの肩書きを持っています。
とくに、教育学者ということもあり「日本」についてかなり詳しい知識を持っています。「声に出して読みたい日本語」は知っている方も多いと思います。
最初にそもそも「アウトプットってなに?」という方へ。
アウトプットとは「話す」「書く」などです。
たとえば・・・
- 人に本で良かったことを「話す」
- ブログで地元の名物を「書く」
などです。
皆さんも普段からしていることです。
著書では「アウトプットするコツ」を劇的に成長する85の方法を提示しています。
この記事では、85の方法をすべて提示することができません。とくに「参考になった!」というものを3つお伝えしたいと思います。
著書の結論

最初に著書の結論について私の解釈をお伝えします。
この「アウトプットするコツ」という本を一言でいうと、
「当事者意識を持とう」ということです。
具体的に説明するまえに、どうして「アウトプット」が必要なのか?これについてお話してきます。
著書ではこう語られています。
「かつては知識豊富な人は尊敬されていましたが、いまやスマホ片手にネット検索すればいつでもどこでも簡単に正確な知識を得られる時代です。
知識が豊富なだけでは大した価値を生まないようになっています。
大切なのはその知識と知識を掛け合わせて、新しい何かを生み出すことです。
そのためにもインプットした知識をどんどん発信していくことで気づきを得ることができます。
つまり「結果を出すためにはアウトプットが必要」ということです。
とはいえ、「会社でアウトプットしているよ」「授業でたくさん話してる書いてる」という方も多いと思います。
ただ、それでは足りないといっています。
著書ではインプットよりも「アウトプットを優先」を提示しています。
一般的な日本人は「インプット9」「アウトプット1」の割合と思います。また、気がつけば「インプットばかり」で「アウトプットをしていない」という人もたくさんいます。
著書では「インプット1」「アウトプット9」の割合を目指そうといっています。
当事者意識を持とう
著書ではアウトプットをするときに1番大切なことは「自分のこと」という当事者意識を持つことといっています。
なぜなら、人は自分のことだと意識したときにアウトプットをします。
たとえば、どんなに心理学の勉強をしてもその知識を使わなければ意味がありません。
どんなに本を読んで知識を得てもそれを「ふうん」と見ているだけでは意味がありません。
「自分ごとにする」これが大切です。
常に自分ごととして当事者意識を持っていれば、「これからどうするのか」と考えることができるようになります。
「これからどうするのか」はアウトプットする上で大切であり、あなたに「前を向いて歩き続ける」唯一の力となります。
参考になったポイント3つを紹介

質より量
1つ目は質より量です。
あなたは話すことや書くことが得意ですか?
それとも苦手意識がありますか?
著書では、「日本人には話すことにも書くことにも苦手意識を持つ人が多くインプット過多アウトプット不足の人がとても多い」といっています。
たしかに、そうですよね。
ではどうして、アウトプットに苦手意識があるのでしょうか?
著書では原因が3つあるといっています。
アウトプット苦手意識の原因①「遠慮しがち」
「人の前で意見を主張するなんて迷惑だ」「私は大した人間ではない」
こう感じる人もいると思います。
アウトプット苦手意識の原因②「恐怖心」
人は「間違うこと」への恐怖心があります。
間違えたくないと言う気持ちが強い人ほど、何か発言するときに「ブレーキがかかって」しまいます。
間違えるくらいなら「発言しないほうが良い」と考える人も多いです。
また、日本人は「恥をかきたくないと言う心理」があります。
そのために「沈黙」選んでしまいます。
アウトプット苦手意識の原因②「アウトプットする心構えができていない」
私たちは小学校から大学生になるまでアウトプットが求められる機会は多くありません。
ただ聞いているだけの授業ではアウトプットする機会はありませんよね。
原因はこの3つです。
とはいっても、
「アウトプットが苦手な原因はわかったけど、どうしようもない」
と思う人もいるでしょう。
残念ながら「遠慮もない」「恐怖心もない」「心構えもいらない」そんな魔法のような答えはありません。
ただ、1つだけアウトプットを苦手意識をなくす方法があります。
それは「アウトプットの量を増やす」です。
なぜなら、アウトプットの量こそが力となるからです。
アウトプットすることで、インプットした情報が脳の記憶に定着しやすくなり、自分の成長を見れて楽しくなるでしょう。
とはいえ、もちろん「そもそもアウトプットが怖いのにたくさんできない!」というのはわかります。
ただ、私はブログとラジオの投稿をしています。始めてから1ヶ月ぐらい経ちましたが、ぜんぜん見られません。
つまり「なにも怖くない」ということです。見られる頃には自分の力も上がっているでしょう。
発疹の不出来についてはあまり考えないようが良いです。
大事な事は「とにかく始めること」
最初は完璧を目指さないよう、5割の出来でぜんぜん問題ありません。慣れてきたらどんどん上がっていきます。
アウトプット前提のインプット
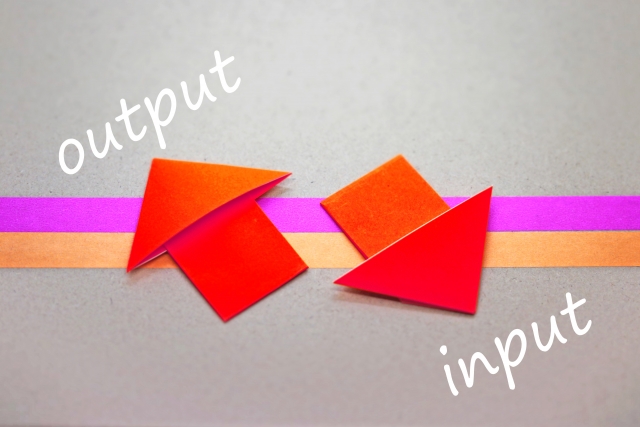
2つ目は「アウトプット前提のインプット」です。
どういうことかといいますと、アウトプットを優先させることで「必要に迫られて」インプットするようになっていきます。
あなたも「インプットするだけで終わる」ということを経験したことがあると思います。
たとえば、本を読むだけで終わる、勉強するだけで終わる、ネット記事を見ただけで終わる、これではインプットしたことを自分のものにできません。
「アウトプット前提のインプット」が大切です。
著書では「インプット1」「アウトプット9」の割合を目指そうといっています。
具体的には「本を10ページ読んだらそれを要約をする」「ノウハウを知ったらその日に実行する」などです。
アウトプットこそが結果を出します。
つまり、高速でインプットとアウトプットのサイクルを回し続けることで「あなたは圧倒的に成長」できます。
専門家を名乗ろう
3つ目は「専門家を名乗ろう」です。
本書ではプロでなくても小説家を名乗ろうと言っています。
なぜなら、アウトプットする事はアイデンティティーを作るための行為であるからです。
たとえば、書籍を紹介するブログなどを書いている場合は「ブロガー」、ラジオ配信「DJ」、本を書いて「作家」と名乗っても良いと言っています。
ただ、ここで1つ疑問があります。
とくに実績があるわけでもないのに「ブロガー」「DJ」「作家」を名乗るのは気恥ずかしいと考えている人も多いと思います。
著書では、「現実には有名な文学賞受賞したからといって小説家だけで食べているわけでもなく、むしろ兼業作家として活動している方が多数派」といっています。
あなたも「自分の強みを活かして専門家」を名乗ってみてはいかがでしょうか。
最後に:現代は恵まれている
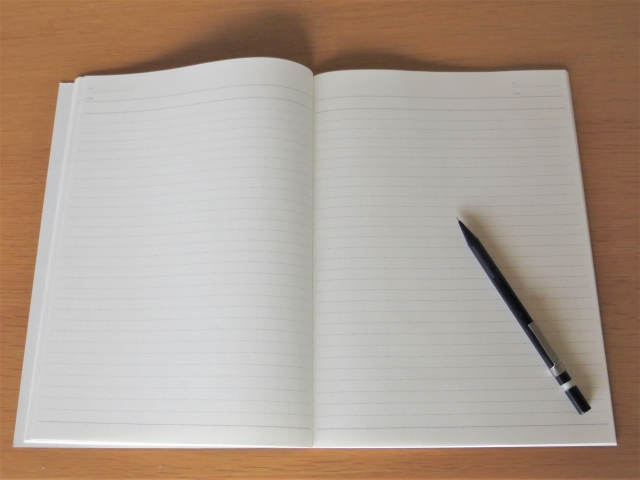
今回は齋藤孝さんが著書「アウトプットする力」という本を紹介しました。
著書ではアウトプットするコツとして85の方法を提示しています。
今回はその中の3つをお伝えしました。
- 質より量を
- アウトプット前提のインプット
- 専門家を名乗ろう
アウトプットが苦手な方、結果を出したい方、そんなあなたにおすすめの1冊です。
ぜひ読んでみてください。
最後に私から「現代は恵まれている」ということで1つお伝えします。
すごい時代がきた
それは「すごい時代がきた」です。
ここでいうすごい時代とは「情報発信することが珍しくなくなった」ということです。
たとえば、本を出版するとき。
「自分の書いた原稿を出版社に出して評価されないと世の中に出せない」
「学者、著名人、有名人などしか書けない」
「出版社から本を出しませんか?という依頼が来ないと出せない」
という状況でした。
ただ、いまはどうでしょうか?
「ブロガーやYouTuberが本を出版するようになった」
「無名でもKindleなどで本を出版できる」
こんな変化があります。
X(旧Twitter)やFacebookなどでも誰もが当たり前のように、自分を発信しています。
つまり現代は「アウトプットの機会に非常に恵まれている」ということです。
こんなチャンス見過ごすわけにはいきません。
これはもう、下克上です。無名でも同じ舞台に立てるようになりました。
もちろん、評価されたいのなら努力は必要ですが、もし、アウトプットして成功をつかみたいのなら、やってみる価値はあるでしょう。
ということで以上となります。





