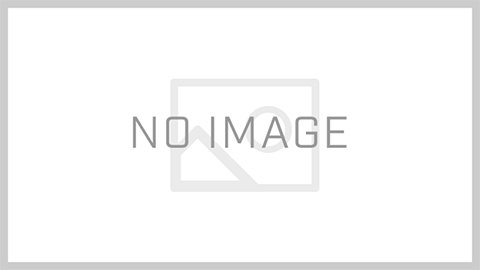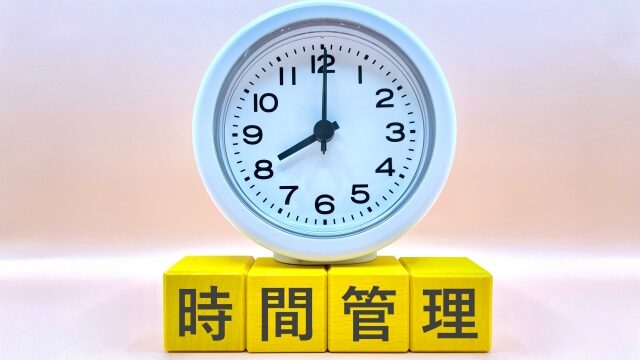【書評】知識を操る超読書術

「本を読みきれない方」
「本を効率的に読んで学びたい方」
「ビジネスのパフォーマンスを上げたい方」
今回は、メンタリストDaiGoさんの著書「知識を操る超読書術」という本をご紹介いたします。
DaiGoさんは1日に10冊から20冊読んでいる圧倒的な方です。
なぜ、そんなことができるのだろうか?
それは「スキミング(拾い読み)」を行っているからです。
スキミングとは、読む本、読む箇所を減らした上で、読むべき箇所を集中的に読み込むことです。
要は選ぶ力です。自分が知りたいところだけを読む方法をスキミングといいます。
具体的な手順は
- 表紙や帯を読む
- 目次を読む
- 気になる1つの章を読む
「この読み方だと本をすべて読むことができない」
大前提として、本はすべて読まなくて良いです。
小説ならともかく、ビジネス本や実用書は「自分が知りたいところだけ」を読めば十分です。
本を読むのがゴールではありません。すべてを読むと時間がなくなります。また、集中力がなくなり、自分が知りたい情報を記憶に定着しにくくなります。
本書に書かれている内容は、基本的に「科学的根拠」に裏づけられているため、信頼性も高いです。それに加えて、誰もが実践できるものばかりです。
- 本を読みきれない方
- 本を効率的に読んで学びたい方
- ビジネスのパフォーマンスを上げたい方
こんな悩みを持つ方はぜひ本書を見ると良いでしょう。
この記事では、「読書にまつわる3つの誤解」「スキミングの深掘り」「本は準備が7割」という3つのテーマでお伝えします。
読書にまつわる3つの誤解

速読に関する誤解
速読とは「速く読むこと」です。
世間では「速く読めるようになれば読書量は増え、必然的に賢くなれて成功する」と思破れているかもしれません。速読の本はたくさんありますよね。
ただ、速読には大きな嘘があります。
本書に書かれている研究データでは、速読に関して以下の結果を出しています。
- 読むスピードを上げると、読んだ気になるだけで内容の理解度はむしろ下がる
- 読書のスピードと時間を決める要素の中で、目の動きや周辺視野が占めるのは10%以下しかない
要は「速く読んでも本の内容は頭に残らない」ということです。
さらに、速読に関して「文章を読むスピードは4分の3が遺伝子で決まる」という調査結果があります。
残念な事実ですが、「本を速く読んで理解すること」は難しいといえるでしょう。
ただ、本書では読むべき箇所を減らす「スキミング(拾い読み)」を推奨しています。
このスキミングを使用すれば「本を速く読んで理解すること」が可能となります。スキミングは後ほど深く解説します。
多読に関する誤解
多読とは「たくさん読む」です。
「速く読めればたくさん読める。たくさん読めれば知識も増える」というのは誤解です。
読書家のタイラー・コーエンは「読めば読むほど1冊あたりの情報の価値は低下する」と言っています。
これは「読めば読むほど新しい情報は少なくなり、読むべき本が少なくなるため、本の価値が減る」ということです。
多読を目指すよりも、読む前の「準備」を大切にしたほうが良いといいます。そうすれば「少ない情報から多くの知識を得る」ことができます。
「準備」については後ほど解説します。
ここまで聞くと「多読はあまり良い方法ではない」と思われるかもしれません。
ただ、多読も使いようによっては輝き出します。
たとえば、経済学の本を多読して多くの知識を身につけたとしましょう。ある程度の専門的な知識を身につけたら「他のジャンル」を読むと良いでしょう。
なぜなら「複数のジャンルを混ぜることでイノベーションが生まれる」可能性があるからです。
経済学×占い、心理学×数学など、他のジャンルを読むことで革新的な「アイデア」が生まれることもあります。
そう考えると「多読」も良いですね。
選書に関する誤解
選書とは「本を選んで読む」というものです。
前提として「価値のある本」とは「読み手の状況」によって大きく変わります。
たとえば、あるときは読んでも価値がないと思った本が、あるときは自分を大きく変える本になっている、ということはあります。
ここでは「いい本ばかり読めばいいというのは誤解」ということです。
大切なのは「あなたにとって役立つ知識や情報を選ぶ」ことです。
ちなみDaiGoさんは、いい本は教科書として読んで、ダメな本は問題集として使っています。これは「ダメな本はアウトプット用にする」というもので、この本はここがダメ、自分ならこう書くなどをします。
「ダメな本でもアウトプットする」これを意識して読んでいくと、さらに知識が深まるでしょう。
スキミングの深掘り

「スキミング(拾い読み)」とは、読む本、読む箇所を減らした上で、読むべき箇所を集中的に読み込むことです。
自分が知りたいところだけを読む方法のことです。
具体的な手順は
- 表紙や帯を読む
- 目次を読む
- 気になる1つの章を読む
という手順です。ここではさらに深掘りをします。
表紙や帯を読む
タイトルとキャッチコピー、帯に書かれた紹介文をチェックして、その本で伝えたいことを把握する、というものです。
著者のメッセージはこれらのどこかにあります。
目次を読む
目次には本の構造や骨組みが書いているため、目次を拾い読みするだけで本の理解度は高まります。「興味がある!」と思った章や見出しを探しましょう。
復習するとき「目次を見てパッと分かる」本って理解がしやすいです。
気になる1つの章を読む
どこか1つの章を選んで読むというものです。
気になったところならどこでも良いといいますが、おすすめは「本のど真ん中の章」です。
なぜなら、本の「最初の方」は読者を惹きつける内容が盛り込まれている、本の「最後の方」も読書感を良くするため力が入っている、ことが多いです。
ですので、ど真ん中をスキミングして「面白い!」と興味が惹かれたら。その本はあなたに合っている可能性が高いです。
スキミングについて注意点が1点あります。
それは「まったく知らないジャンルはスキミングできない」ということです。スキミングは「自分にとって必要な知識なのか必要がない知識なのか見分ける読み方であるから」です。
要は「読む本の基礎知識を持っている」ことが重要です。
まず、「その本の分野の基礎知識を頭に入れる→スキミングによって読むべき箇所を決める」これが効率的かつ頭に残る読み方になります。
本は準備が7割
知識を得るために本を読むときは「本を読む前の準備」が1番大切です。
知識を得るために本を読むときは「本を読む準備をする→本の読み方を知る→本から得た知識をアウトプットする」このサイクルがベストな学び方になります。
そして「本を読む前」に時間をかけることで、結果的に速く効率的に本を読むことができます。
本書では、本を読む前の準備として「メンタルマップ」「キュリオシティ・ギャップ」「セルフテスト」の3つのテクニックが紹介されています。
詳しくは本書を見ていただきたいと思いますが、簡単に説明します。
メンタルマップ
メンタルマップは何かを箇条書きにして視覚化したものです。
読書を例にすると「なぜこの本を読もうと思ったのか?」「この本を読んで自分はどのようになりたいのか?」と質問して、答えを視覚化することです。
これは良く、自己分析や人生の指針を決めるときに使われることがあります。
キュリオシティ・ギャップ
キュリオシティ・ギャップは「自分が知っている知識」と「自分が知らなかった知識」の差にギャップを感じた、つまり「好奇心を刺激された」ことは記憶に残るというものです。
これを意識することで「読むべき箇所」を把握できます。
セルフテスト
セルフテストは「自分の現在地を知る」というものです。
これは「挫折防止」です。
事前に挫折ポイント知ることで、いざ壁にぶつかったときにすぐに対処できます。本書では10個の挫折ポイントを用意して対処方法をお伝えしています。
まずはとにかく読もう
今回はメンタリストDaiGoさんの著書「知識を操る超読書術」という本をご紹介しました。
本書に、他にも「本の読み方」や「アウトプット方法」などについても書いています。気になる方はぜひ読んでみてください。
最後に、6ヶ月で300冊読んだ私から「まずはとにかく読もう」ということで2つお伝えします。
私もバイブルとなる本以外は、ほとんどはスキミングです。
最初は知らないのが当たり前
1つ目は「最初は知らないのは当たり前」ということです。
新しく何かを学ぼうと思ったら、気合いを入れて評価の高い専門書を買ってしまいがちです。
これは大きな間違いです。なぜなら、「内容が分かりにくい」からです。
最初は「入門書」を読むことをおすすめします。
新しく何かを学ぶときは、つい背伸びをしたいという気持ちはわかります。
私もよくやっていました。その結果、どうなったかというと「部屋に読んでいない本が積まれる」という状況です。
1番の目的は「読む」ことではなく「読んだあと」です。
まずは、楽しく、らくに読める本を読んでいきましょう。
ポチる
2つ目は「ポチる」です。
私は、気になった本はすぐにポチります。
本は1冊1500円ぐらいです。これを高いと思うか安いと思うかは人によって違いはありますが、私は「安い」と思っています。
よく言われることは「本は著者が何年もかけて得た知識やノウハウの宝庫」というものです。
とはいえ、気になった本をすぐに買っていたらお金がなくなってしまうため、「月に10冊買う」「1週間に3冊買う」こんな感じで良いと思います。
ということで以上になります。
知識を操る読書術を得て、最高に成長したいのなら、ぜひ本書を読んでみてください!